その事件は2016年6月12日に東京の荒川区で発生した。
インターネットで注文したロレックスの高級時計を暴力団員が騙し取ろうとした事件だが、屈強な佐川男子に阻まれた事件だ。
今回は、この恐喝未遂事件を再現してご照会致します。
事件の発端
指定暴力団松葉会の組員2人が、モデルガンを使った「偽芝居」を演じて宅配物を騙し取ろうとしたところ、屈強な配達員たちに阻止されてしまった。
組員のA(35)は、インターネットで高級腕時計ロレックス(約86万円)を代金引換で注文した。
脅して取れば犯罪になるが、一芝居打って商品を配達させる(置き配)ことを仕組んだ。
本物の拳銃ではなくモデルガンでもチラつかせれば、配達員もビビって逃げ出すだろうと考えた。
そこで、Aは同じ組のB(32)を引き込み、「偽芝居」を演じることにした。
注文の翌日、佐川急便の配達員2人が荒川区町屋の組事務所に荷物の配達に訪れた。
(2人で配達しているということは危険(組事務所の配達で高額な代引きの荷物)を察知しての配達ですね^^ )
事件の結末
配達された荷物を組員Bが勝手に開け始めた。
それを見た組員AがBに向かって罵声を浴びせながら拳銃を突き付けた。
誰もが組員同士の内輪揉めが始ったと思った。
暴力団の事務所で拳銃を使った揉め事が起きたとなれば、普通の素人は怖がって逃げる、彼らはそう考えたのだ。
ところが、佐川急便の配達員は逃げるどころか、肝っ玉が据わっていた。
まずは、組員Bから商品を取り返した。
そして、逃げる途中で後ろから撃たれないように、組員Aから拳銃を奪い取り、事務所から走って逃げながら110番通報をした。
そのとき、配達員は拳銃がモデルガンであることには気付いていなかったという。
駆けつけた警視庁荒川署員は、その拳銃が「モデルガン」であることを直ぐに看破し、組事務所に乗り込んだ。
組員2人は組事務所から既に逃走していたが、同署の必死の捜査の結果、同年の10月中旬になってやっと逮捕された。
逮捕された組員の供述
組員Aは容疑を認め、「配達員が屈強で敵わなかった」と供述。
組員Bは「Aが勝手にやったことで自分は関係ない」と否認している。
トラブルの気配を察知し屈強な2人の配達員で代引きの荷物を配達
「佐川急便の配達員2人が・・・」という文言を見て、「はてな?」と思われた読者も多かっただろう。
本来、配達先には配達員1人で配達するというのが原則である。
にも拘わらず、このケースでは「不測の事態に備えて」2人の配達員を組事務所に行かせた。(組員も配達場所を組事務所ではなく自宅にしておけばうまくいったかもしれませんね(><:)
もちろん、今回のような「茶番劇」が待っていようとは想像していなかったはずだ。
指定暴力団の組事務所に配達ということで、不測の事態に備えて配達員2人で対応した。
この2人は、佐川急便が選抜した選りすぐりの屈強な配達員だった。
配達員に比べて、2人の組員は体力的にも劣っており、本当に闘ったとしても勝ち目はなかったと言われている。
暴力団事務所への配達を断ることはできないのか?
宅配業者は、それが暴力団であろうと誰であろうと、配達先に荷物を届けるのが仕事だ。
暴力団であっても、何の理由も無いのにいきなり素人に危害を加えることはあり得ないが、用心に越したことはない。
例え相手が暴力団であろうが、配達を拒否することはできない。
そうかといって、組事務に配達するときは、必ず屈強な配達員2人を配置するわけにもいかない。
今回のケースでは、以前にもその組事務所で不穏な動きがあって、佐川急便も警戒していたのではないかと噂されているようだ。
事件の概要はコチラのサイト様を参考にさせていただきました。➔ 屈強な「佐川男子」、暴力団員すら圧倒 世にも奇妙な恐喝未遂事件の一部始終check
今回の事件から学ぶ代金引換の荷物を配達するリスク
「代引き」とは「代金引換」の略で、宅配業者が品物を購入者に届ける際に、その代金を回収し、販売者に振り込むシステムのことである。
代引き決済は、販売業者にとっては、リスクのある取引方法である。
商品の購入者が受取を拒否するケースがある。
頼んだ後で「気が変わった」とか、「支払うお金が無い」など様々な理由がある。
受取拒否による販売者の損失は、
・ 発送時の送料
・ 受取拒否された後に戻って来るまでの送料
・ 発送に掛かった労力と時間
今回のように、「代引き決済」を悪用した詐欺行為は過去にも多く見られる。
ネガティブオプション(送り付け商法)
注文していない商品を勝手に送り付け、受け取った場合は購入したとみなし、代金を請求する詐欺商法も存在する。
健康食品やサプリメント、DVDなどが多く、中には紙切れ1枚や石が入っていたという事例もある。
代引き商品は、受取人本人でなくても、家族などが代わりに代金を払って受け取ることができる。
代金を支払う前に中身を確認することができないため、心当たりの無い荷物は「受取拒否」の対応が必要だ。
また、受取人が不在の場合には、本人の確認が取れるまで受取を保留することが必要だ。
世の中が便利になればなるほど、新たな詐欺や悪徳商法をする輩が現れる。
家族や隣人同士で協力し合いながら防御方法を考えなければならない時代になった。
安易に人を信用できない時代が到来したといえる。





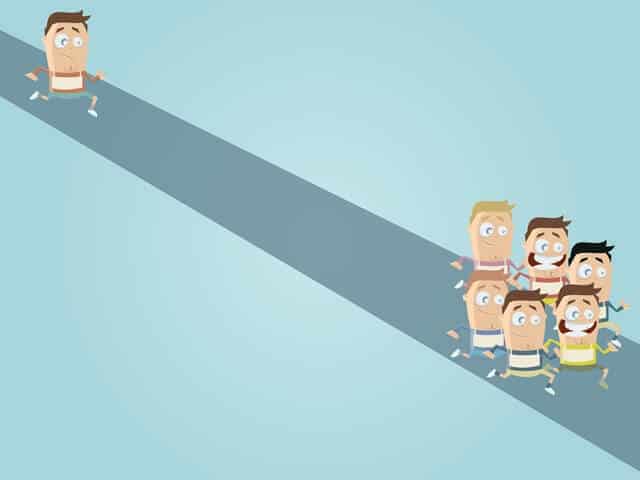





コメントを残す