近年、運送業界は飲酒運転にかなり敏感だ。
飲酒運転はもってのほかだが、前日の飲酒をも禁止している会社も珍しくない。
ドライバーにとっては「仕事の後の一杯」くらいは楽しみたいところであろう。
だが、翌日のことを考えて晩酌さえ躊躇しなければならないドライバーも増えているのが現実だ。
さすがに前日の飲酒くらい、と思うドライバーもいるだろうが、運送会社としては自社のドライバーが「飲酒運転で逮捕された」などと報じられようものなら信用問題になりかねない。
謝って済むような簡単な話ではないからこそ、どの会社も飲酒運転にはデリケートになっている。
しかし、それこそ20年程前までは飲酒運転などそれほど珍しいものではなく、むしろ飲酒していることを武勇伝のように語るドライバーもいたほどだ。
もちろん今では到底考えられないが、これだけ飲酒運転が厳しくなったのには過去の事件がその背景にある。
東名高速飲酒運転事故とは?
飲酒運転が世間でクローズアップされるきっかけとなったのは「東名高速飲酒運転事故」だ。
1999年の11月に起きたこの事件は、加害者であるトラック運転手が飲酒していたことが判明した。
当時の日本道路公団(現在のNEXCO中日本)に「不自然な運転をしているトラックがある」との通報が何件かあり、料金所でも係員が不自然に感じたとのことであった。
結果、加害者が運転する12トントラックが乗用車に追突し、行楽帰りの家族の3歳と1歳の子供が死亡した痛ましい事故であった。
当時はまだ「危険運転致死傷罪」も制定されていなかったため、「業務上過失致傷罪」が適用されたのみで、子供2人が亡くなったにも拘わらず懲役4年という軽い刑であった。
その後、遺族は運転手とその勤務先であった運送会社に対して損害賠償を請求した。
民事訴訟として裁判が行われ、裁判所は原告に対して約2億5,000万円の支払いを命ずる判決を下した。
被告が飲酒運転の常習犯であったことや、運送会社の取締役が酒気帯び運転で追突事故を起こしたことなどが厳しい判決が下された理由となったようだ。
この追突事故は被害者家族が被告が勤務していた運送会社の従業員に対して飲酒運転根絶を訴える講演を行ったわずか3週間後に起きたものであった。
この事件は、飲酒運転の厳罰化に大きな影響を及ぼしたと言える。
2000年に神奈川県の座間市で無免許飲酒運転によって大学に入学したばかりの子供を亡くした遺族は、飲酒運転の刑罰を重くする為の署名運動を起こした。
当時、飲酒運転に関しては適用される罪が業務上過失致死しかなかったため、どうしても量刑が軽くなっていた。
そこで座間市の被害者遺族が立ち上がり、法改正を求める署名運動を展開したのだ。
当時は飲酒運転がニュースやワイドショーでも取り上げられていたことから、37万を超す署名が集まり、それを法務大臣に提出した。結果、世論に後押しされる形で「危険運転致死傷罪」が制定されるに至った。
危険運転致死傷罪は、最高で懲役15年。
遺族としてはそれでも「まだまだ刑罰が軽すぎる」との思いはあろう。
しかし、少なくとも「業務上過失致死」と比べれば重い刑罰が制定されたことについては遺族の思いが通じたのではなかろうか。
それでも飲酒運転は根絶出来ていない
危険運転致死傷罪が制定されたからといって飲酒運転が無くなったかといえば、答えは「No」だ。
いかなる法律であろうとも、結局は「見つからなければOK」なのが現状だ。
最近では誰もがスマートフォンを持っており、怪しい車がいれば静止画だけではなく動画で撮影し、直ちに警察に通報ができるようになった。
それでも「見つからなければOK」と平然と飲酒運転をしているドライバーもいることだろう。
もちろんそれは「トラックのドライバー」という意味ではなく、「車を運転する」全てのドライバーのことだ。
世論が動けば法律も変わる
東名高速飲酒運転事故で亡くなられた遺族に対してはお気の毒ではあるが、それによって世論が動き、新しい法律が制定されることとなった事実は否めない。
行政側ではなく、世論が動いたことで行政が対応した形だが、今後も飲酒運転での事故が繰り返されれば更なる厳罰化もあり得る。
事実、飲酒運転の罪はもっと重くするべきであると考えている人は多い。
運送業界のドライバーは一般のドライバーと比べてハンドルを握っている時間が長い。
従って事故を起こす、或いは事故に巻き込まれる可能性はどうしても高くなる。時には「どうしても避けられない」と思える事故もある。
どれだけ自分自身が注意をしていても防げない事故はある。
車が逆走してきたり、飲酒運転に巻き込まれてしまう可能性はゼロではない。
しかし、自分自身の飲酒運転は防げる。
一部の運送会社で前日の飲酒まで禁止していることに対しては、厳し過ぎると思う反面、「もしも」のことを考えれば致し方ないこととも考えられる。
ドライバー不足やネット通販による荷物の増加などにより、ドライバーという仕事が決して楽ではない、とうことも一般に知られるようになった。
公務員が飲酒運転を犯す原因とは?
最近は、運送会社のドライバーより公務員が飲酒運転を犯して社会問題になることが多い。
原因の一つに地方の飲み会が挙げられている。
地方公務員は、歓送迎会、忘年会、新年会、町会内の総会、などなど役所の飲み会や地域の飲み会が多い。
都心に比べて地方は終電時間も早く飲んだ後に車で直帰する習慣も未だ根強いのではないか?と思う。
然しながら地方公務員が飲酒運転で逮捕されれば懲戒免職になる確率が極めて高い。
運送会社のドライバーは、飲酒運転が所属する会社に発覚すれば懲戒解雇になり失職して運送会社に再就職することも極めて難しい。
公務員は運転が本職ではないから高をくくり「まさか?クビにはならないだろ?」、と安易に思っていても不思議ではない。
しかし、飲酒運転をして社会的信用や職を失うのは余りにもリスクが高い。(2019年11月11日改訂)





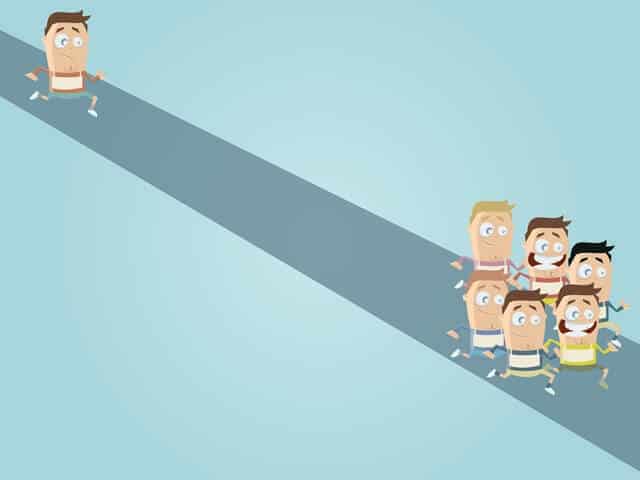





コメントを残す